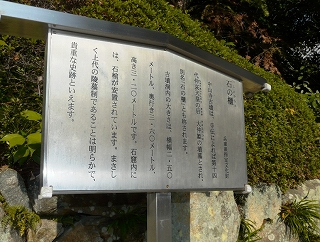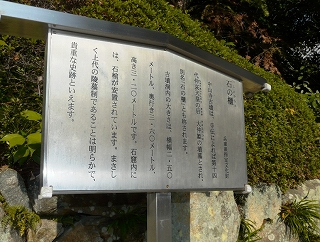ニュース
(2013.12.1)
◇第625回観察会が宝塚市中山から清荒神方面で行われました。
12月1日(日)、午前9時30分に阪急宝塚線中山駅に集合。師走とは思えないような穏やかな晴天に恵まれました。
北側出口付近に集まり、地図を見ながら本日のコースと観察される主な植物について説明をしたあと出発。中山寺の立派な山門をくぐると、参道に沿って植えられたコウテイダリアが私たちを迎えてくれました。境内は参拝者でにぎわっています。しばらく進むと、列植されたコウテイダリアの後ろの石垣にツメレンゲが開花していました。よく見ないと見落としてしまいそうです。階段を上り詰めると、左手に中山寺古墳が見えてきます。古墳を囲む石垣にはトキワトラノオとノキシノブがたくさん着いていました。また、石垣の上にはフユノハナワラビがありました。
信徒会館の前を通り、梅林を右に見ながら進むと、ツツジの花が一輪咲いていました。どうもヒラドツツジとモチツツジの雑種のように見えます。足洗川を渡り、しばらく行くと、シンボル広場が見えてきます。足下にはクヌギとアベマキの落ち葉が見られ、その違いを確かめました。今日はここから、奥の院コース(尾根筋の道)を行きます。
日当たりのいいところの木々が見事に紅葉しています。コツクバネウツギやイソノキの紅葉がこれほど美しいとは思いませんでした。樹木に絡みついたアマヅルの葉は真っ赤です。コバノガマズミとソヨゴが赤い実をつけ、ヒサカキには黒い実と来年の花芽が観察されました。道端にはアキノキリンソウが咲き、シハイスミレが季節外れの花を咲かせていました。ツクシハギの花もわずかに残っていました。この付近一帯は土壌の発達が悪く、足下は岩がごろごろしています。シダ類は比較的少なく、やや湿った所にコハシゴシダ、ヤワラシダ、ホラシノブ、ベニシダ、オオベニシダなどが見られました。
やがて夫婦岩園地に到着。眼下には、伊丹空港や猪名川が望まれました。付近のコナラはきれいに紅葉し、空の青とのコントラストが見事です。
小休止の後、出発。シャシャンボの熟した実を口に含むと、甘酸っぱい味が広がります。しばらく行くと夫婦岩です。ウラジロノキが赤い実を着けています。その名のとおり、葉の裏の白い綿毛が目立ちます。中山連山には多い樹木です。その近くで、初冬の柔らかい日差しを受け、春と勘違いしたのか、コバノミツバツツジが数輪開花していました。この付近はコバノミツバツツジが多く、春にはツツジのトンネルができます。カナメモチ、ザイフリボク、リョウブの実も観察されました。道端のシャシャンボの幹にヒノキバヤドリギが着生していました。この辺りでは、ソヨゴの幹などにも着生しています。近くから観察でき、格好の被写体となっていました。クロモジの葉が黄色く色付き、翌年の花芽も観察されます。北摂の山地では、ヒメクロモジは確認していません。立派な花芽を付けたモチツツジが真っ赤に色付いています。こんなに見事に紅葉するとは思っていませんでした。コウヤボウキ、ネジキ、ガンピ、ネズミサシなどを観察しながら少し行くと、管理道路に沿ってナナカマドやドウダンツツジが植栽されていました。赤く色付いてきれいですが、自然豊かな山の中に植栽するのは大いに問題があると思います。
やがて、中山奥の院と最高峰の分岐点に到着。少し早目の昼食となりました。付近には、タムシバ、ホオノキの実生が見られます。また、ナツハゼがたくさん実を付けており、食後のデザートとなりました。
 |
 |
| コウテイダリア |
ツメレンゲが生育する石垣 |
 |
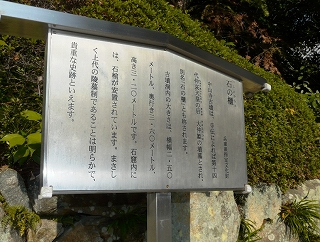 |
| ツメレンゲ |
中山寺古墳 |
 |
 |
| トキワトラノオ |
フユノハナワラビ |
 |
 |
| ヒラドツツジ×モチツツジ? |
コツクバネウツギ |
 |
 |
| イソノキ |
アマヅル(オトコブドウ) |
 |
 |
| コバノガマズミ |
ソヨゴ |
 |
 |
| ヒサカキ |
アセビ |
 |
 |
| アキノキリンソウ |
ツクシハギ
|
 |
 |
| シハイスミレ |
コハシゴシダ |
 |
 |
| ヤワラシダ |
オオベニシダ(後ろはベニシダ) |
 |
 |
| 夫婦岩園地 |
シャシャンボ |
 |
 |
| ウラジロノキ |
カナメモチ |
 |
 |
| コバノミツバツツジ |
ザイフリボク |
 |
 |
| リョウブ |
ヒノキバヤドリギ |
 |
 |
| クロモジ |
コウヤボウキ |
 |
 |
| ナナカマド(植栽) |
モチツツジ |
 |
 |
| タムシバ |
ホオノキの実生 |
 |
 |
| ナツハゼ |
冬芽の観察 |
午後12時30分に出発。直接奥の院へ向かうメンバーを見送り、私たちは中山最高峰への分岐点を経て奥の院へと向かいました。尾根筋のコースは岩が露出し、両側からウラジロとコシダの群落が迫る独特の景観が見られます。よく見ると、湿った法面にウラジロ・コシダの前葉体と幼植物が育っています。赤い実に気付き、ふと見上げると、カマツカの実が真っ赤に色付いていました。この辺りから実をたくさん付けたクロバイが現れます。
尾根筋であるため、樹高はさほど高くありませんが、かなりの古木です。立派なヤマモモも現れます。アカガシ、ウラジロガシの大木が続き、やがて足下に、裏が白いホオノキの落ち葉が目立つようになります。見上げると、天を突くように大木が聳え、背後には立派なアカマツも見られました。
最高峰への分岐点を左にとり、尾根道を奥の院へと向かいました。中山連山にはタムシバが多く、枝先に花芽がたくさん着いていました。早春には真っ白い花が咲き、春の訪れを知らせてくれます。タカノツメ、ウリカエデ、ツクバネウツギ、スノキなどが黄色く色付いています。ヤブムラサキの葉腋には瑠璃色の実が輝き、足下にはツルアリドオシが真っ赤な実を付けていました。
やがて中山奥の院に到着。残念ながら、現在は立て替え工事中のため、拝殿を見ることはできません。境内のイチョウ、オオモミジ、イロハモミジの大木の紅葉・黄葉は、まるで絵のようです。石垣には、ヘビノネゴザ、オオイタチシダ、ヤマイタチシダ、ハシゴシダ、ツルドクダミなどが見られ、キチジョウソウが開花していました。
奥の院をあとに、やすらぎ広場を経て清荒神清澄寺方面へ向かいます。モミジの色付き方も様々です。黄色地に赤い覆輪が入るイロハモミジがありました。谷筋では、ヤマツツジが数輪開花し、イヌツゲの実が黒く熟していました。途中に険しいガレ場がありましたが、皆さん無事に下山され、午後3時過ぎに大林寺に到着しました。
ここで一応解散となりました。ここから清荒神駅までは約30分。清荒さんにお参りをして帰路に着いた方もありました。柔らかい日差しを受けた山々の紅葉を見ながら駅へと向かいました。本日の参加者は31名でした。
 |
 |
| ウラジロ、コシダ |
ウラジロ(幼植物) |
 |
 |
| カマツカ |
クロバイ |
 |
 |
| アカガシ |
ホオノキの観察 |
 |
 |
| ホオノキ |
タムシバ |
 |
 |
| タカノツメ |
ウリカエデ |
 |
 |
| ツルアリドオシ |
イチョウ、オオモミジ、イロハモミジ |
 |
 |
| ヘビノネゴザ |
ツルドクダミ |
 |
 |
| キチジョウソウ |
イロハモミジ(赤い覆輪) |
 |
 |
| ヤマツツジ |
イヌツゲ |
 |
| 荒神さんの山々の紅葉 |
(本文・写真 山住一郎)
 |
| 中山寺奥の院・最高峰分岐にて |